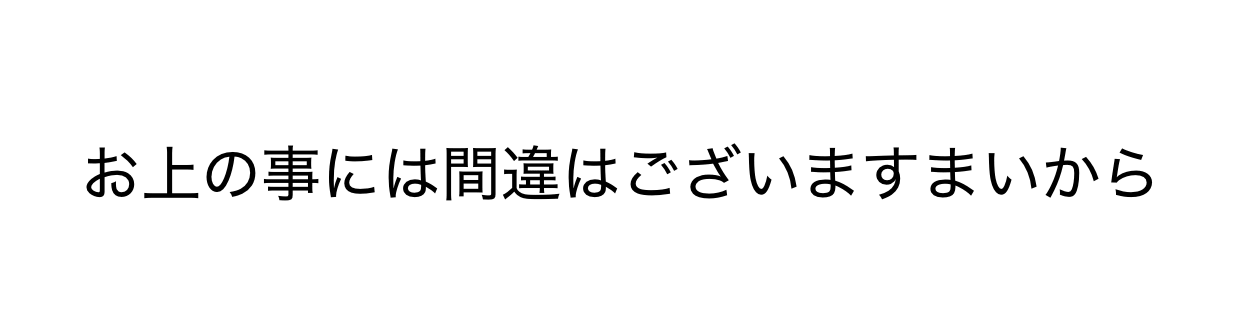
森鴎外の短編小説『最後の一句』は大正四年に発表された。「殉職(マルチリウム)」という観念が未開である元文頃の徳川時代、みずからを犠牲に他人を救うという行為は、人々にどのように捉えられるのか。斬罪を宣告された父を救うため、自己犠牲を厭わない十五歳の娘・いちの言動が、役人一同の胸を刺す。
外部リンク:森鴎外『最後の一句』青空文庫
『最後の一句』の要約
船乗業の桂屋太郎兵衛が斬罪に処せられることが知らされた。罪状は、太郎兵衛の船で業を営むものが、航海の途中で難船したことに託けて、海に流失したとされる積荷を売り金にし、その金を太郎兵衛が受け取ってしまったからである。
太郎兵衛の十六歳の娘いちはお父さん(太郎兵衛)を救おうと、じぶん等五人の兄弟姉妹が代わりに罪を受けるという願書を奉行(役人)に届け出る。いち等は、その願書の経緯について役人から尋問を受けることになり、その殺伐とした厳しい状況下においても、いちの言動は冷静沈着であり、その信念は確固不動としている。
元文頃(1736〜1741年)の徳川家の役人は、殉教や献身という観念をもたないため、いちの言動を奇妙に思ったが、それでも胸を刺すものがあり、晴れていちの父は死罪を免れることになる。
『最後の一句』の解説
太郎兵衛の娘・いちの言った〈お上の事には間違はございますまいから〉という最後の一句は、いちの一生をお父さんのみならずお上にも委ね献呈することになる。この一句は、いちの抱いている信念を確固不動たるものとして、その言葉の威光を煌々と光り輝かせた。
もし、いちが最後の一句を言わなければ、いちの書いた願書はお上に受理されなかったであろう。殉教という観念が未開とはいえ、役人等は、いちの行為を単純に父を慕うゆえの抵抗作用として一見落着するからである。
現代において殉教は至高の難儀である。
ややもすると親をもまるで他人と思う現代においては、いちのように自己の生命と引き換えに親の生命を救うこと、あるいはその逆で、親が子を救う行為とは無益にほかならず、その首に高額な生命保険がぶら下がっている場合は急逝を願う人もいる。あらゆる信念の価値が底をついた時代にどうして他人のために身を献ずることができるだろうか。たとえそれが子であれ親であれとも。
殉教のように自己の死さえを厭わない行為は、生物の本来のものではない。本来のものに抵抗している。しかし、そういう本来の流れに従わず、流れに逆行する行為というのは、殉教の意味を知らずとも知っていようとも人の胸を深く刺すものである。
令和二年 十一月
関連記事:『妄想』の要約と解説と感想

コメント